
花粉症の時期に眠気やだるさの症状があらわれる原因と対処法
花粉症の時期に眠気やだるさの症状があらわれる原因
花粉症の時期に眠気やだるさの症状があらわれる原因には、以下のようなことが考えられます。
|
・自律神経の乱れが原因によるもの ・花粉症の症状が原因によるもの ・抗ヒスタミン薬の副作用が原因によるもの |
自律神経の乱れが原因によるもの
スギ花粉が多い冬から春にかけては、気温差が激しいため、自律神経の乱れによる眠気やだるさが起こりやすい時期でもあります。
自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、日中や活動しているときは交感神経が優位に働き、夜やリラックスしているときには副交感神経が優位に働きます。
これらの自律神経のバランスが、激しい気温差により崩れることで、眠気やだるさを感じやすくなると考えられます。
花粉症の症状が原因によるもの
花粉症の主な症状には、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの鼻の症状と、目のかゆみ・充血などの目の症状があります。
また、鼻・目の症状以外にも、のどや皮膚のかゆみ、頭重感、だるさ、熱っぽさの症状があらわれることがあります。
これらの症状のなかで、眠気を引き起こす主な原因となっているのが、鼻づまりによる睡眠への悪影響と考えられています。
抗ヒスタミン薬の副作用が原因によるもの
花粉によるアレルギー症状に使用される薬として市販されているのが、抗ヒスタミン薬とよばれる薬です。
抗ヒスタミン薬には、アレルギー反応の原因となるヒスタミンの作用を抑える働きがありますが、副作用として眠気の症状が現れる可能性があります。
副作用として眠気の症状が現れる理由は、集中力や覚醒の維持という役割を持つ、脳内のヒスタミンの作用も抑えてしまうためです。
花粉症の時期におこる眠気やだるさへの対処法
花粉症の時期におこる眠気やだるさに対処する方法には、体への花粉の侵入を防ぐほか、眠気の副作用が比較的少ない抗ヒスタミン薬を選ぶなどがあります。
体への花粉の侵入を防ぐ
体への花粉の侵入を防ぐことは、睡眠に悪影響を及ぼす可能性のある、鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの花粉症の症状の悪化を防ぐことにつながります。
花粉の飛散が多い時期は外出を控える、外出するときはマスクやメガネを着用する、帰宅したら花粉を洗い流すなどして、体への花粉の侵入を防ぐようにしましょう。
また、枕のまわりの花粉をふき取る、空気清浄機を使用する、外に布団を干すのを控えることも、体への花粉の侵入を防ぐ効果的な方法です。
眠気止め薬を使用したり、仮眠をとったりする
すでにある眠気や倦怠感をどうにかしたい場合は、眠気や倦怠感の除去効果のある市販薬(トメルミン®︎*1やエスタロンモカ®︎*2など)を使用したり、仮眠をとったりするのも一つの手です。
ただし、眠気や倦怠感を除去する市販薬は短期間の服用にとどめ、連用しないようにしましょう。
なお、眠気や倦怠感により、日常生活に悪影響が出ている場合は、病院を受診するようにしましょう。
眠気の副作用が比較的少ない抗ヒスタミン薬を選ぶ
一般に花粉によるアレルギー症状には、抗ヒスタミン薬が使用されていて、鼻水、鼻づまりなどの鼻の症状や、目のかゆみ・充血などの目の症状に効果をあらわします。
抗ヒスタミン薬は、効果や副作用の特徴によって第1世代と第2世代にわけられています。
第1世代の抗ヒスタミン薬は、眠気や口が渇くなどの副作用が比較的あらわれやすい薬です。
第2世代の抗ヒスタミン薬は、第1世代の効果をなるべく維持しつつ、第1世代の特徴であった眠気や口が渇くなどの副作用が比較的あらわれにくくなっています。
そのため、眠くなりにくい抗ヒスタミン薬を探している場合は、第2世代の抗ヒスタミン薬がおすすめです。
*効果の感じ方や眠気などの副作用には個人差があるため、注意が必要です。
ケアビエンは『フェキソフェナジン塩酸塩』を配合した、第2世代の抗ヒスタミン薬です。比較的眠くなりにくいことが特徴です。
フェキソフェナジン塩酸塩が花粉やハウスダストなどによる、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのつらい鼻のアレルギー症状を改善します。
ケアビエンは、無理なく続けられるリーズナブルな価格です。
■花粉症の市販薬の選び方
以下の記事では、第2世代の抗ヒスタミン薬や、アレルギー用目薬、点鼻薬(季節性アレルギー専用)の選び方などについて紹介しています。
※1 トメルミンはライオン株式会社の登録商標です。
※2 エスタロンモカはエスエス製薬株式会社の登録商標です。

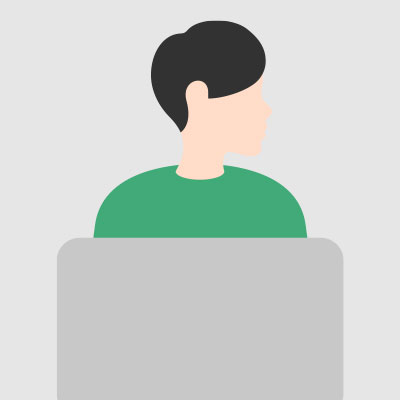
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。


