
動脈硬化とは?原因・予防法・コレステロール値を改善する市販薬を解説
動脈硬化ってどんな病気?
動脈硬化は余分なLDL(悪玉)コレステロールなどが血管壁に蓄積し、血管が硬くなってしまった状態を指します。
動脈硬化が進行すると、血管が狭くなることで血流が悪くなる、血管が傷ついてしまうリスクが高くなります。
動脈硬化は重篤な病気を引き起こす
動脈は身体の各器官に酸素や栄養素、血液を運ぶ役割を果たしています。
動脈硬化によって血流が滞ると身体の各器官に栄養が行き届かなくなり、機能低下を起こして重篤な病気を引き起こすおそれがあります。
脳卒中や心筋梗塞などがそれに当たり、場合によっては死にいたる危険性もあります。
生活の中で考えられる原因
動脈硬化は加齢による血管の老化に加え、コレステロールのバランスが悪くなる脂質異常症、糖尿病、高血圧などの病気が原因になることがあります。
これらの病気は生活習慣病と呼ばれ、乱れた生活習慣が原因となることが多い病気です。
肥満
肥満とは、体重が多いだけではなく、体脂肪が過剰に蓄積した状態を言います。
肥満の中でも内蔵の周囲に脂肪がたまる内臓脂肪型肥満は、生活習慣病や動脈硬化と深い関係があるといわれています。
■肥満度の判定について
肥満度の判定には、BMI(Body Mass Index)という指標が用いられています。
| 肥満度の判定に 用いられる指標 | BMI(Body Mass Index)=[体重(kg)]÷[身長(m)2] |
|---|
標準とされるBMIは22であり、肥満との関連が強い生活習慣病に最もかかりにくい数値とされています。
また『脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上のもの』が肥満と定義づけられています。
ただし、目指す体重は個人によって異なるため、まずは医師に相談するとよいでしょう。
食生活の乱れ
摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ることが肥満につながります。
特に肉類や乳製品などにかたよった食事や、食べすぎ・不規則な時間の食事などは動脈硬化を進行させる原因になります。
喫煙
喫煙は、血管の壁が損傷を受けて血が固まりやすくなります。また、動脈硬化から発症する心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因となります。
さらに喫煙は、血中の総コレステロールやLDL(悪玉)コレステロールを増やし、HDL(善玉)コレステロールを減らすことも知られています。
動脈硬化の予防方法
動脈硬化は生活習慣を改善することによって、ある程度予防することが可能です。
特に健康診断等でLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)の値が高かった方は、動脈硬化のリスクが高くなっているため、次のことに注意するようにしましょう。
食生活を改善する
■飽和脂肪酸・トランス脂肪酸が含まれる食品について
飽和脂肪酸が多く含まれる肉の脂身や、工業的に作られたトランス脂肪酸の多い食品(スナック菓子、バター等)の過剰な摂取に注意が必要です。また、塩分のとりすぎにも注意しましょう。
動脈硬化の原因となる、コレステロール値を改善するためにおすすめの食事に関しては、次の記事で詳しく解説しています。
■食物繊維について
野菜や海藻類などに多く含まれる食物繊維は、コレステロールの吸収を妨げ体外に排出する働きがあります。
食物繊維には水溶性と不溶性の2種類がありますが、その中でも余分なコレステロールを排出するのにおすすめなのが水溶性食物繊維です。
食生活が不規則な人は、特定保健用食品(トクホ)から、水溶性食物繊維の摂取をしてもよいでしょう。
なお、健康診断等でコレステロール値が高いと診断された方は、服用前に医師・薬剤師等に相談してください。
運動をする
運動には有酸素運動(ウォーキングなど)とレジスタンス運動(スクワットなど)があります。
脳心血管病の予防には、両者を併用することが勧められています。両者の運動の要素が含まれている階段上りを日常に取り入れるのもよいでしょう。
強さとしては楽〜ややきつい程を目安に、有酸素運動は1日30分以上、レジスタンス運動は10〜15回を2〜4セットを行いましょう。
ただし、運動の強度や時間は個人の体力を考慮する必要があるため、はじめる前には医師に相談してから行いましょう。
禁煙をする
禁煙は脳心血管病を予防し、動脈硬化の進行を防ぐ大きな対策になります。
コレステロール値を改善する市販薬
コレステロール値の改善方法はあくまでも食事と適度な運動ですが、補助的な意味でコレステロール値をコントロールする市販薬を活用するのも1つの方法です。
| 有効成分 |
|---|
| イコサペント酸エチル |
エパデールTは、健康診断等で指摘された境界領域※1の中性脂肪値を改善する医薬品です。
エパデールTの有効成分であるイコサペント酸エチルには、肝臓での過剰な中性脂肪合成を抑え、血中の余分な中性脂肪の代謝をはやくして中性脂肪の値を改善する作用があります。
医薬品の効果は個人差があるため、本剤の服用開始3ヵ月後には、医療機関等で血液検査を行い、中性脂肪値の改善を確認してください。
※1健康診断などにおいて中性脂肪が正常値よりもやや高めの値(150mg/dL以上300mg/dL未満)のこと
| 有効成分 |
|---|
|
パンテチン 大豆油不けん化物 酢酸d-α-トコフェロール |
コレストンは3種の有効成分を配合しています。
血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢神経障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
大豆由来成分の大豆油不けん化物が腸からの余分なコレステロール吸収を抑え、排泄をうながします。
また、パンテチンがコレステロール代謝を改善し、酢酸d-α-トコフェロールは血行を促進することで手足に冷えやしびれを緩和します。
医薬品の効果は個人差があるため、服用後は医療機関で定期的にコレステロール値の測定をすることをおすすめします。
薬を服用しても生活習慣の改善は必須
薬は血液中のコレステロールや中性脂肪が多い状態を治すわけではなく、あくまでコントロールをしているだけです。根本的な原因を解消するためには、食事療法と運動療法は必須となります。
薬を服用しても食生活の改善と適度な運動は継続するようにしてください。

昭和大学大学院薬学研究科修了
昭和大学薬学部客員講師
株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局
薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。
【著書】
•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬
•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル
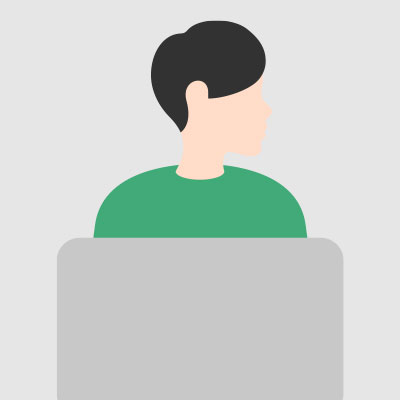
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。



