
当帰芍薬散の効果と副作用は?成分や飲み方もわかりやすく解説
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)は、足腰の冷えや腰痛、貧血、生理不順、月経痛、更年期障害など、女性に多い症状に使用されている漢方薬です。本記事では、当帰芍薬散の効能・効果や、副作用、用法・用量などを解説します。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)とは?何に効く?
当帰芍薬散は、貧血の改善や月経異常、冷え性などに使われている漢方薬です。
全身の血の巡りを良くすることに加え、体内の水分量を整える働きがあります。
女性に多い症状に処方される漢方
当帰芍薬散は、産婦人科系の疾患に効果が示されている三大漢方薬の一つで、当帰(トウキ)、芍薬(シャクヤク)などの6つの生薬が配合されています。
「血(けつ)」を補い、「水(すい)」を巡らせる
漢方では古くから、「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」と呼ばれる3つの要素が体内をめぐることにより、健康を保っていると考えられています。
全身に酸素や栄養分を運び、体を温めるものを「血」と呼び、「血」は現代医学でいう「血液」と同様の概念です。
当帰芍薬散は、「血」「水」の乱れを改善するために用いられている漢方薬です。
「血」が乱れると、「血」が不足して血色が悪くなったり、乾燥して肌につやがなくなったりします。
また、「血」が巡らずに滞ると、冷え性や月経痛、月経時の血塊などの症状がみられます。
「水」の乱れとは、身体の中の「水」がうまく巡らない状態であり、あらわれる症状は、むくみやめまい、耳鳴り、頭痛などです。
当帰芍薬散の効果・効能
市販薬の当帰芍薬散(ツムラ・クラシエ)の添付文書によると、効果・効能は以下のとおりです。
体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
当帰芍薬散の効果・効能について解説します。
貧血傾向の改善
当帰芍薬散には、補血作用があるため、貧血と疑われる方や、疲れやすい方に使用されます。
女性は月経があるため、男性よりも「血」が不足しやすく、貧血症状が出やすい傾向にあります。
ただし、血液検査で貧血(鉄欠乏性貧血)と診断された場合には、鉄剤などによる治療が必要です。
月経痛・月経困難症の改善
月経痛(生理痛)や月経困難症、それに伴う下腹痛、腰痛、頭重、疲労脱力感、更年期障害によるイライラや憂鬱などの精神症状といった症状にも、当帰芍薬散が使用されます。
月経痛や月経困難症を悪化させる要因に「冷え」や「血行不良」がありますが、当帰芍薬散に含まれる生薬には、それらを改善し、症状の緩和を促す働きがあります。
月経不順の改善
月経不順とは、月経周期が長すぎたり短すぎたりと周期が乱れることで、要因の一つが「血」の不足です。
当帰芍薬散で「血」を補うことで、月経不順の改善が期待できます。
むくみ、足腰の冷え、腰痛、めまい、耳鳴りの改善
体を巡る「水」が滞ると、全身の不調を引き起こします。
たとえば、下肢に「水」が滞るとむくみや末端の冷えが生じ、頭や耳に「水」が溜まると頭重感やめまいなどが生じる、などです。
当帰芍薬散は、「水」の巡りをよくする作用があるため、むくみや足腰の冷え、冷えによる腰痛、頭痛、めまい、耳鳴りなどを改善します。
更年期障害の改善
当帰芍薬散は、更年期障害の効能・効果が認められています。
更年期障害の症状は、以下のとおりです。
| 更年期障害の主な症状 |
|---|
| ・ホットフラッシュ(顔のほてり、のぼせ) ・異常発汗 ・倦怠感、不安、憂鬱、イライラ ・不眠、睡眠障害 ・頭痛、めまい、耳鳴り ・動悸、息切れ ・肩こり、腰痛、関節痛 ・手足の冷え、しびれ など |
なお、当帰芍薬散は、「虚証(きょしょう)」と呼ばれる虚弱体質や疲れやすい体質の方には向いていますが、「実証(じっしょう)」と呼ばれる、体力があり筋肉質でガッチリしている方には向きません。
「実証」に向く、桂枝茯苓丸や他の漢方薬についてはこちらの記事で紹介しています。
当帰芍薬散の副作用
当帰芍薬散には、以下のような副作用が報告されています。
【当帰芍薬散(市販薬)の副作用】
| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
|
皮膚 |
発疹・発赤、かゆみ |
|
消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |
市販薬の当帰芍薬散を服用後に上記の症状が出現した場合は、副作用の可能性があります。
服用を中止し、医師や薬剤師、登録販売者に相談してください。
当帰芍薬散の飲み方
ここでは当帰芍薬散の用法・用量に加え、どのくらいの期間服用すればよいのかを解説します。
用法・用量
当帰芍薬散の用法・用量は製品によって異なります。
ここでは一例として、市販薬のクラシエとツムラの用法・用量を紹介します。
市販薬のクラシエ当帰芍薬散錠は、1日3回服用です。
【クラシエ当帰芍薬散錠の用法・用量】
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
|
成人(15歳以上) |
4錠 |
3回 |
|
15歳未満7歳以上 |
3錠 | |
|
7歳未満5歳以上 |
2錠 | |
|
5歳未満 |
服用しないこと | |
上記の量を1日3回、食前または食間に水または白湯で服用しましょう。
市販薬のツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒 23 は、1日2回の服用です。
【ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒 23 の用法・用量】
| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|
|
成人(15歳以上) |
1包(1.875g) |
2回 |
|
7歳以上15歳未満 |
2/3包 | |
|
4歳以上 7歳未満 |
1/2包 | |
|
2歳以上 4歳未満 |
1/3包 | |
|
2歳未満 |
服用しないこと | |
上記の量を食前に水またはお湯で服用します。
どれくらいの期間飲む?
当帰芍薬散の効果が出るまでの期間は、個人の体質や症状の経過によって異なりますが、1か月程度使用しても症状が改善しない場合は、薬が合っていない可能性があるため、医師や薬剤師、登録販売者に相談してください。
当帰芍薬散についてよくある質問
当帰芍薬散を服用するうえでのしてはいけないことや、服薬する際に注意が必要な人など、よくある質問やその回答を紹介します。
してはいけないことはある?
小児に内服させるときは必ず保護者の指導監督のもと服用させてください。商品によっては服用できる年齢が異なる場合があるため、添付文書を確認してください。
また、授乳中の方は乳児への影響も考えられるため、医師に相談してから服用を検討してください。
併用できない薬はありませんが、当帰芍薬散以外の漢方薬も併せて服用する際は、生薬の過剰摂取になるおそれがあるため注意が必要です。
服用に注意すべき人は?
以下に該当する人は、市販の当帰芍薬散を服用する前に医師や薬剤師に相談が必要です。
- 医師の治療を受けている人
- 胃腸の弱い人
- 過去に、薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
当帰芍薬散は皮膚症状と消化器症状の副作用が報告されています。
胃腸が弱い方や薬により発疹・発赤、かゆみなどの症状があらわれたことのある人は、服用前に医師や薬剤師へ相談しましょう。
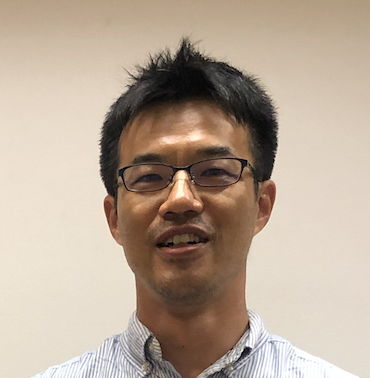
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。




