
子ども用の酔い止め薬|選び方も紹介
子ども用の酔い止め薬の選び方
子ども用の酔い止めには、様々な成分が含まれており、成分によってそれぞれ特徴が異なります。酔い止めを使う目的に合わせて、以下のポイントを見ながら選びましょう。
対象年齢
子ども用の酔い止めは、3歳、5歳、7歳、11歳以上などと薬によって服用できる年齢が分かれています。さらに、子どもから大人まで使えるファミリー用もあります。薬によって対象年齢が異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、子どもが使える酔い止めには、飲みやすいように味や剤形を工夫している薬もあります。
服用回数
車やバスによる比較的短時間の移動で必要に応じてこまめに服用したいなどの場合は、1日2、3回飲める酔い止めがおすすめです。
一方、旅行中に何回も服用するのは面倒だ、飛行機などの長旅で途中で効果がきれない方がよいなどといった時は、1日1、2回のタイプをおすすめします。
眠くなりやすい薬か?眠くなりにくい薬か?
酔い止めに含まれている成分のひとつに、抗ヒスタミン成分があります。抗ヒスタミン成分は、めまいなどの乗り物酔いの症状をおさえ、眠くなりやすいという特徴もあります。
移動中ゆっくり休みたい、車や船に乗っている間に寝てしまうことで乗り物酔いを回避したいなどという場合は、抗ヒスタミン成分配合の眠くなりやすいタイプをおすすめします。
ただし旅行で移動中も会話や景色を楽しみたい、現地での観光中に眠くなってしまうと困る、などという時は、眠くなりにくいタイプを選ぶとよいでしょう。
酔い止めの役割
酔い止めには、乗り物の揺れやスピードによって引き起こされる平衡感覚や自律神経の乱れを調整し、乗り物酔いを予防したり、酔った時の症状を緩和したりする役割があります。
酔い止めに含まれている主な成分には、抗ヒスタミン成分や抗コリン成分があります。抗ヒスタミン成分は、脳の嘔吐中枢の興奮をおさえ、内耳前庭での自律神経反射を抑制するため、吐き気(嘔吐)やめまいなどの症状を緩和します。抗コリン成分は、副交感神経を抑制して自律神経の乱れを調整し、主に乗り物酔いの症状を予防します。
乗り物酔いの対策には、事前の体調管理や食事のとり方、乗り方の工夫などもありますが、乗り物酔いをしないためにも、酔い止めを上手に活用しましょう。
子どもにおすすめの酔い止め薬
乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛に効く薬を紹介します。以下の特徴を参考にしていただきながら、酔い止めを使う目的にあわせて選びましょう。
センパア プチベリー
| 特徴 |
|---|
|
✔️3歳から大人まで ✔️1日2回まで ✔️乗り物酔いの予防にも使える ✔️ラムネのようにかんで飲める(いちご風味) |
抗ヒスタミン成分『クロルフェニラミンマレイン酸塩』が配合されているため、眠くなりやすいです。移動中にゆっくり休みたい方におすすめです。
抗コリン成分『スコポラミン臭化水素酸塩水和物』が主に乗り物酔いの症状の予防に効きます。
3歳以上の家族みんなで使えます。お出かけ前や、途中で気分が悪くなった場合にも、水なしでその場ですぐに服用できます。また、いちご風味のため、薬特有の味が苦手なお子様にもおすすめです。
トラベロップQQ S
| 特徴 |
|---|
|
✔️5歳から大人まで ✔️1日2回まで ✔️乗り物酔いの予防にも使える ✔️水なしで服用できるサイダー味のドロップ |
抗ヒスタミン成分『d-クロルフェニラミンマレイン酸塩』が配合されているため、眠くなりやすいです。移動中にゆっくり休みたい時におすすめです。
抗コリン成分『スコポラミン臭化水素酸塩水和物』が主に乗り物酔いの症状の予防に効きます。
5歳以上の家族みんなで使えます。また、お出かけ前の予防として、また気分が悪くなったときでも水なしで服用できるドロップタイプの薬です。サイダー味のため、苦い味が苦手なお子様にもおすすめです。
トラベルミン・ジュニア
| 特徴 |
|---|
|
✔️5歳から14歳まで ✔️1日3回まで ✔️酔った時の症状に ✔️小さな錠剤 |
大人用のトラベルミン同様、抗ヒスタミン成分『ジフェンヒドラミンサリチル酸塩』が配合されているため、眠くなりやすいです。移動中にゆっくり休みたい時におすすめです。
また、『ジプロフィリン』が揺れによって起こる感覚の混乱を抑制し、めまいなどを軽減します。
5歳から14歳まで服用できる小さな錠剤の薬です。お子様用におすすめです。
センパア トラベル1
| 特徴 |
|---|
|
✔️7歳から大人まで ✔️1日1回まで ✔️乗り物酔いの予防にも使える ✔️水なしで飲める(グレープフルーツ風味) |
抗ヒスタミン成分『クロルフェニラミンマレイン酸塩』が配合されているため、眠くなりやすいです。移動中にゆっくり休みたい方におすすめです。
抗コリン成分『スコポラミン臭化水素酸塩水和物』が主に乗り物酔いの症状の予防に効きます。
7歳以上の家族みんなで使えます。1日1回の服用のため、お出かけ前の服用で済みます。さらに、水なしで服用できるチュアブル錠のため、つらい乗り物酔いの時でもおすすめです。
トラベルミンR
| 特徴 |
|---|
|
✔️11歳から大人まで ✔️1日2回まで ✔️乗り物酔いの予防にも使える ✔️比較的眠くなりにくい |
抗コリン成分『スコポラミン臭化水素酸塩水和物』が副交感神経を抑制して自律神経の乱れを調整し、吐き気などが起こらないようにします。その他にも、酔った時の症状を緩和する成分が配合されています。
11歳以上の子どもや大人に使えます。比較的眠気の少ない成分が配合されているため、移動する間も旅行を楽しみたい、眠くなるのは困るという方におすすめです。
酔い止めは何歳から使える?
乗り物酔いは3歳頃から始まり、小学校高学年や中学生で多くなり、成人になると少なくなると考えられています。そのため、酔い止めによっては3歳から服用できる薬があります。
3歳未満は脳が未発達であるため、ほとんど乗り物酔いをしないといわれています。万が一お出かけ中に吐き気などを訴えた場合は、乗り物酔いではない可能性もあるため、一度医療機関の受診をおすすめします。
酔い止めを飲むタイミング
酔い止めを乗り物酔いの予防として飲む場合は、乗る30分前に服用してください。
また、乗り物酔いの症状がでた時に飲む場合は、薬の説明書(添付文書)にある用法・用量を守って飲むようにしましょう。
使用上の注意
子どもだけでなく、大人も服用する際の注意点を紹介します。
酔い止めを服用後は、眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状が現れることがあるため、乗り物または機械類の運転操作をしないでください。
また、薬によっては服用に注意が必要な方や服用してはいけない方もいるため、気になる場合は医師や薬剤師にご相談いただくか、服用前に添付文書をご確認ください。
他の薬との飲み合わせ
次の薬については成分が重なるため、酔い止めを服用している間は服用しないようにしてください。
- 他の乗り物酔い薬
- 風邪薬
- 解熱鎮痛薬
- 鎮静薬
- 鎮咳(ちんがい)去痰薬
- 胃腸鎮痛鎮痙(ちんけい)薬
- 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
乗り物酔いの対策
乗り物酔いの対策としては、酔い止めをあらかじめ服用しておくことが効果的ですが、乗り物酔いをしやすい方は次の点にもご注意ください。
- バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないよう気をつけましょう。
- 当日は、食べすぎたり、空腹になったりしないよう、適量の食事をとりましょう。
- 座席は、揺れの少ない前方の席や換気のよい窓側の席に座りましょう。
- 窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりなどで気分をまぎらわしましょう。

昭和大学大学院薬学研究科修了
昭和大学薬学部客員講師
株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局
薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。
【著書】
•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬
•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル
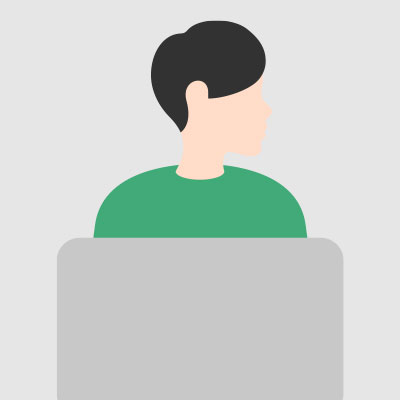
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。







