
慢性的に痰が絡む原因は?|対処法や病院に行くタイミングを紹介
慢性的に痰が絡む原因は?
痰が絡む原因は、自動車の排気ガスや工場現場などの粉塵、タバコの煙などがあげられます。また、風邪をひいたときも痰が出ますが、長くは続きません。
慢性的に痰が絡む場合は、なんらかの病気が原因になっていると考えられます。原因として考えられる病気には、以下のようなものがあります。
|
・慢性閉塞性肺疾患(COPD) ・気管支喘息 ・慢性副鼻腔炎 ・通年性アレルギー性鼻炎 など |
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主にタバコの煙などの有害物質を、長期間吸うことにより発症する病気で、痰を伴う咳が続く、少しの動きでも息切れをしやすくなるなどの症状があらわれます。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)では、黄色や粘り気のある痰がでます。
気管支喘息
気管支喘息は、アレルギーなどが原因で発症する病気で、咳や痰、呼吸困難、喘鳴(のどがゼイゼイと鳴る)などの症状が発作的にあらわれます。
気管支喘息では、透明または白っぽい痰がでます。
慢性副鼻腔炎
慢性副鼻腔炎は、主に細菌感染が原因で発症する病気で、鼻がつまる、膿が混じった鼻水がでる、頭重感などの症状があらわれます。
慢性副鼻腔炎では、膿が混じった鼻水が喉に流れることにより、咳や黄色の痰がでることがあります。
通年性アレルギー性鼻炎
通年性アレルギー性鼻炎は、主にダニやカビ、ペットなどに対するアレルギーが原因で発症する病気で、くしゃみや水のような鼻水、鼻づまりなどの症状があらわれます。
通年性アレルギー性鼻炎では、水のような鼻水が喉に流れることにより、咳や白っぽい痰がでることがあります。
痰が絡む症状が続く場合は病院を受診
以下のような場合は、病院を受診しましょう。何らかの病気が原因で、痰が絡む症状が続いている場合があります。
|
・痰が絡む症状が3週間以上続いている ・黄色や緑色などの粘り気のある痰が出る ・痰に血が混じっている など |
なお、痰が絡む状態を放置したり、原因がわからないまま市販薬を使用して咳をとめたりすると、病気を進行させてしまうおそれがあります。
痰が絡む症状が続く場合や、風邪・鼻炎・喫煙など痰がからむ原因が思い当たらない場合は、病院を受診し原因をはっきりとさせることが大切です。
痰が絡む場合の対処法
痰が絡む場合には、気道への刺激を緩和したり、市販薬を使用したりすることで、症状の緩和が期待できます。
部屋の乾燥を防ぎ、水分摂取を多めにおこなう
部屋の空気が乾燥していると、痰が外に出にくくなります。部屋を加湿して、空気の乾燥を防ぎましょう。
また、痰を出しやすくするためには、意識して水分を摂取することも大切です。水分を摂取することで、痰の粘り気が減り、痰が出しやすくなります。
禁煙するなどして気道への刺激を和らげる
痰が絡む症状を緩和させるためには、気道への刺激を和らげることも大切です。気道への刺激を和らげる方法には、以下のようなものがあります。
|
・空気の乾燥する冬場にはマスクを着用する ・アレルゲン除去のために空気清浄機を設置する ・たばこを吸っている方であれば禁煙をする など |
■禁煙が難しい場合は市販の禁煙補助薬の使用も
禁煙が難しい場合には、市販の禁煙補助薬を使用するのも一つの方法です。
禁煙補助薬を使用すると、禁煙開始後の離脱症状が緩和されるため、薬を使わない場合に比べて禁煙をおこないやすくなります。
■市販で購入できる禁煙補助薬
市販で購入できる禁煙補助薬には、ニコチンパッチとニコチンガムがあります。
ニコチンパッチは体に貼り皮膚からニコチンを吸収させることで、ニコチンガムは口の粘膜からニコチンを吸収させることで、禁煙開始後の離脱症状を緩和します。
禁煙補助薬の選び方や、使用方法については、以下の記事で解説しています。
市販薬を使用する
痰が絡む症状を緩和させるためには、去痰成分が配合された市販薬を使用するのも一つの手段です。
去痰成分には、気道粘膜からの分泌液をうながしたり、痰の粘り気を減らしたりすることで、痰を出しやすくする作用があります。
去痰成分が配合された市販薬については、以下の記事で紹介しています。

昭和大学大学院薬学研究科修了
昭和大学薬学部客員講師
株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局
薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。
【著書】
•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬
•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル
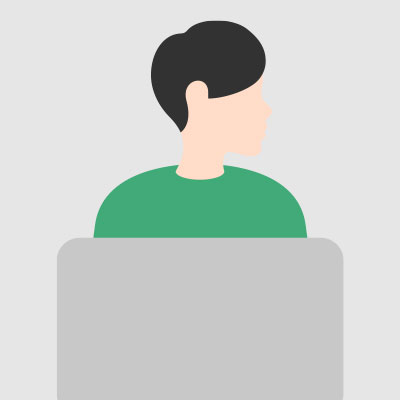
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。


