
子どもには湿布が使えない?|子どもでも使用できる湿布を紹介
子どもには湿布が使えない?
市販の湿布には、配合されている成分によって、子どもに使用できる湿布と使用できない湿布があります。
例えば、解熱鎮痛成分の一つであるNSAIDsが配合された、ボルタレン®EXテープやボルタレン*ACαテープでは15歳未満の子どもの使用が、サロンパス®EXでは11歳未満の子どもの使用が禁止されています。
一方で、解熱鎮痛成分の一つであるサリチル酸グリコールや、サリチル酸メチルが配合された湿布は、子どもでも使用できます。
このように市販の湿布は、配合されている成分によって、子どもに使用できる湿布と使用できない湿布があります。
子どもに湿布を使用するときは、使用前に添付文書を確認して、子どもに使用できるか確認しましょう。
NSAIDsとサリチル酸グリコール、サリチル酸メチルの作用の違い
NSAIDsとは、非ステロイド性抗炎症薬と呼ばれるもので、痛みや炎症のもととなるプロスタグランジンの生成を抑えることにより、痛みを和らげたり、炎症を抑えたり、熱を下げたりする作用があります。
サリチル酸グリコールとサリチル酸メチルには、冷たさによって皮膚表面の感覚を鈍らせることで、痛みを和らげる作用があります。
サリチル酸グリコールとサリチル酸メチルでは、作用の違いはありませんが、サリチル酸グリコールのほうが湿布独特のにおいが少ないという特徴があります。
| 成分 | 特徴 |
|---|---|
| NSAIDs |
・商品によって15歳未満もしくは、11歳未満の子どもへの使用が禁止されている ・痛みや炎症のもととなるプロスタグランジンの生成を抑える ・痛みを和らげる作用、炎症を抑える作用、熱を下げる作用 |
| サリチル酸グリコール サリチル酸メチル |
・子どもでも使用できる ・冷たさによって皮膚表面の感覚を鈍らせる ・痛みを和らげる作用 ・サリチル酸グリコールのほうが湿布独特のにおいが少ない |
子どもでも使用できる湿布
サロンパスAe
痛みを緩和する成分であるサリチル酸メチルや、血行を促進するビタミンE酢酸エステルなどが配合された湿布です。
肩こりや腰痛のほか、打撲やねんざ、筋肉痛、関節痛などに効果をあらわします。
サロンパス30
痛みを緩和する成分サリチル酸グリコールや、血行を促進する成分ビタミンE酢酸エステルなどが配合された湿布です。柔軟性があり、肌にフィットしやすい素材です。
微香性なので貼ったままでも気になりにくく、外出したい日にも便利です。
肩こりや腰痛のほか、打撲やねんざ、筋肉痛、関節痛などに効果をあらわします。
パテックスうすぴたシップ
痛みを緩和する成分サリチル酸グリコールや、清涼感をもたらす成分l-メントールなどが配合された湿布です。衣類にからみつきにくい超薄型タイプです。
肩こりや腰痛のほか、打撲やねんざ、筋肉痛、関節痛などに効果をあらわします。
サロンパス30ホット
痛みを緩和する成分サリチル酸グリコールや、温感成分トウガラシエキスなどが配合された湿布です。
マイルドな温感刺激が肩こりや腰痛、筋肉痛などに効果をあらわします。
なお、温感成分であるトウガラシエキスで、まれに刺激を感じることがあります。刺激を感じた際は、使用を控えてください。
子どもに湿布を使用するときの注意点
子どもに湿布を貼るときには、以下の点に注意しましょう。症状の悪化につながったり、副作用が起こりやすくなったりするおそれがあります。
|
・汗や水気をしっかりとふき取ってから貼る ・粘膜や傷がある場所、かぶれがある場所には貼らない ・湿布を剥がしたあとすぐに次の湿布を貼らない ・かゆみや、かぶれの症状があらわれたらすぐに使用を中止する など |
湿布以外でできる打撲・捻挫、筋肉痛などへの対処法・予防法
打撲・捻挫や筋肉痛などには、湿布を使う以外にも氷を入れたビニール袋で冷やす、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるなどの対処法・予防法があります。
打撲・捻挫への対処法
打撲・捻挫をしたときは、まずRICE(ライス)と呼ばれる4つの応急処置を行いましょう。
すぐに処置をするかしないかで、その後の経過に違いが出ることがあるため、応急処置をすることが大切です。
1.安静(Rest)
打撲・捻挫したところを動かさないようにします。腕の場合は三角巾やタオルなどで吊り、足の場合は松葉杖を利用するなどして負担がかからないようにします。
2.冷却(Ice)
打撲・捻挫した箇所より少し広めの範囲を、氷を入れたビニール袋や、冷却パックなどで冷やしましょう。炎症を鎮め、痛みをやわらげることにつながります。15〜20分を目安に、冷やしすぎないように注意し、断続的に患部を冷やしましょう。
3.圧迫(Compression)
打撲・捻挫したところを、適度に圧迫しながら、包帯やテーピングで固定しましょう。患部の腫れや、内出血の予防につながります。圧迫しすぎると、血行が悪くなることがあるので注意しましょう。
4.高く上げる(Elevation)
打撲・捻挫したところを、心臓より高くあげることで、内出血や痛みの緩和につながります。椅子やクッションを利用して、無理のない高さを保ちましょう。
筋肉痛の予防法
筋肉痛を予防するためには、運動をした日に、ぬるめのお湯にゆっくり浸かったり、筋肉を構成する原料となるタンパク質や、血行を改善するビタミンなどを多めにとったりすることが大切です。
肩こりの予防法
スマホなどを長時間使用すると、肩こりの原因になります。スマホなどを長時間使用するときは、定期的に休憩をはさんだり、ストレッチをしたりして首周りの筋肉をほぐすことが大切です。
また、慢性的な肩こりがあるときは、湯船で体を温めたり、カイロや蒸しタオルで肩まわりを温めたりするのが効果的です。
体を温めると血液のめぐりが良くなるため、慢性的な肩こりの解消につながります。
腰痛の予防法
長時間同じ姿勢でいると、腰に負担を与えてしまう原因になります。長時間作業するときは定期的に立ち上がる、姿勢を変えるなどして腰への負担を減らすことが大切です。
また、腰痛を予防するためには、有酸素運動や筋トレ、ストレッチ運動などを定期的に行うことが大切です。
関節痛への対処法
子どもの関節痛の原因のひとつである成長痛に対しては、患部をさすってあげたり、軟膏や湿布を使用してあげたりすることで、痛みの緩和につながります。
関節痛の原因が成長痛であれば、治療の必要はありませんが、何らかの病気が原因の場合、適切な治療が必要になるため、病院で診察をうけて原因を特定することが大切です。
※1ボルタレンはノバルティス アクチエンゲゼルシャフトの登録商標です。
※2サロンパスは久光製薬株式会社の登録商標です。

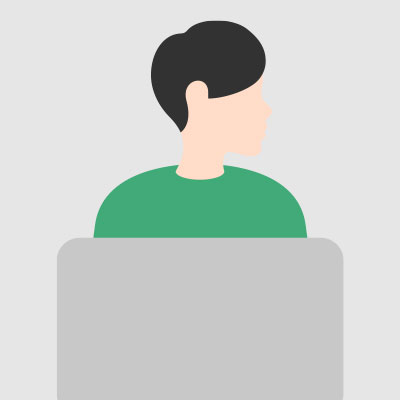
この記事は参考になりましたか?
新着記事
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。





