
床ずれ(褥瘡)に使用できる市販薬はある?原因や治療法、注意点を解説
床ずれとは?好発部位はお尻(尾てい骨)や肩など
床ずれは、医学用語で褥瘡(じょくそう)といいます。
ふとんやベッド、車イスなどに長時間同じ体勢で寝たり座ったりしていると、皮膚が触れ続けている部分に体重による圧迫がかかり、血流が悪くなります。
圧迫され続けた部分の皮膚や皮下組織には十分な酸素や栄養が届かず、その部分はただれたり、傷ができたりしてしまいます。
特に、自分で寝返りができない寝たきりの方などに多くみられ、体の中でも骨が突出した部位で起きやすいのが特徴です。
床ずれが特に起こりやすい場所は「お尻(尾てい骨)」「頭部」「肩」「膝」「かかとなど足回り」です。
軽い床ずれでは、皮膚が赤くなるだけのときもあります。
褥瘡であるのかを確かめるには、指で赤くなっている部分を軽く3秒ほどおし、白っぽく変化するかどうかを確認します。押したときに白く変化し、離すと再び赤くなるものは褥瘡ではありませんが、押しても赤みが消えずそのままの状態であれば、初期の褥瘡の可能性があります。
床ずれ治療の進め方
床ずれの治療は、症状の段階ごとに行われます。
床ずれが起きてから約1~3週間を急性期といいます。急性期にうまく治療できれば、そのまま治ることもありますが、そのまま慢性期へと移ってしまうこともあります。
慢性期は床ずれの深さが真皮までにとどまる「浅い床ずれ」と、真皮より深くまでおよぶ「深い床ずれ」に分けられます。
浅い床ずれは、ほとんどの場合短期間での治癒が可能ですが、深い床ずれは治癒までに数か月の時間がかかり、状態が悪いと治癒まで1年以上かかる場合もあります。
深い床ずれは治療が進むごとに「黒色期→黄色期→赤色期→白色期」と移り変わり治癒していきます。
急性期の治療
急性期は床ずれが発生して間もないときで、発赤、紫斑、浮腫、水疱、びらん、浅い潰瘍などが主な症状です。
治療はまず床ずれが起きた原因を探し出し、その原因を取り除くことが重要です。
すでに起きている急性期の床ずれや浅い床ずれにはドレッシング材や塗り薬、ガーゼによる患部の保護が行われます。
黒色期~黄色期の治療
「黒色期」は壊死した組織が黒くなり、皮膚についた状態の時期です。この黒い組織が取り除かれ、壊死した脂肪組織が見えた状態の時期を「黄色期」といいます。
この時期は壊死組織を除去することと感染制御を行い、肉芽組織が早く形成される環境を整えることが大切です。
壊死組織の除去はメス、電気メス、ハサミによる外科的な除去や外用薬やドレッシング材によって行われます。
赤色期~白色期の治療
「赤色期」は肉芽組織という血管に富む組織が、欠損した部分を埋めるように成長し傷が治っていく時期です。
「白色期」になると傷周辺から皮膚ができて傷は治癒に向かいます。
赤色期~白色期では、患部の適度な潤いの保持と患部の保護を行い、肉芽組織や皮膚ができるような環境を整えます。
また、肉芽形成を促進させる塗り薬などの使用することで治療を進めます。
その後は硬い皮膚の「傷あと」になります。この治癒したばかりの皮膚は弱くなっていて、床ずれになりやすい状態です。
床ずれが治った後も褥瘡予防のケアを続けていくことが大切です。
床ずれ治療薬:ドレッシング材と塗り薬
床ずれの治療の基本は「傷口の保護」と「傷口の程良いうるおいの維持」です。保護のためによく使用されるのが、ドレッシング材といわれる傷口を覆うフィルムと塗り薬です。
ドレッシング材と塗り薬は種類が豊富で、それぞれに特徴があり、床ずれの状態によって細かく使い分けられています。
塗り薬
塗り薬はそれぞれ役割が違うため、傷口の状態や使う目的に合わせて医師が選びます。
患部の保護を目的として塗り薬を使う場合は「白色ワセリン」「亜鉛化軟膏(酸化亜鉛)」「アズノール軟膏0.033%(ジメチルイソプロピルアズレン)」などの油脂性基剤軟膏を使います。
感染対策が目的の場合は「ゲーベンクリーム1%」などの外用薬が使用されます。
また患部から滲み出る体液が過剰な場合は、体液の吸収作用・殺菌作用のある「カデックス軟膏0.9%」「ユーパスタコーワ軟膏」などで対応していきます。
このように塗り薬は症状に合わせて、細かく使い分けられています。
| 主な塗り薬 | 主な目的 |
| ・亜鉛化軟膏 ・アズノール軟膏0.033% | ・患部の保護目的など |
| ・プロスタンディン軟膏0.003% | ・患部の保護目的 ・皮膚の形成を促進させる目的 |
| ・ゲーベンクリーム1% |
・抗菌作用(滲出液が少ないとき) |
| ・アクトシン軟膏3% | ・皮膚の形成を促進させる目的 |
| ・ユーパスタコーワ軟膏 ・カデックス軟膏0.9% | ・殺菌作用(滲出液が多いとき) |
ドレッシング材
ドレッシング材は、キズを覆うことで、外部からの刺激や細菌の汚染などを防ぎます。近年ではキズが治るのに最適な環境とされる、湿潤環境を維持することのできる、高機能なものも多く販売されています。
清潔なキズから出てくる滲出液は傷の治りを早くするものなので、適切な量をキズ周囲に保持することで、キズのなおりを促進することができます。
ただし過剰な浸潤は治癒に悪影響を及ぼす可能性があり注意が必要となります。また、傷口が細菌感染などを起こしている場合は逆効果になるため、細菌感染を起こしていないこと確認しましょう。
ドレッシング材は、それぞれに浸出液を吸うことのできる量、性質が異なりますので、キズの深さや浸出液の量によって様々なものを使い分けます。
| 主なドレッシング材 | 種類 | 主な目的 |
| ・オプサイトウンド ・パーミエイド | ポリウレタンフィルム | ・傷口の保護 |
|
・デュオアクティブ | ハイドロコロイド | ・傷口の閉鎖と湿潤環境 |
| ・ニュージェル ・グラニュゲル | ハイドロジェル | ・乾燥した傷口の湿潤 |
| ・ハイドロサイトプラス | ポリウレタンフォーム | ・滲出液の吸収 |
| ・アクアセルAg ・アルジサイト銀 | 銀含有ドレッシング材 | ・感染抑制作用 |
在宅での床ずれ治療:市販薬は使用できる?
在宅介護で床ずれが起きた場合は、皮膚が少し赤い程度の軽い床ずれであれば市販薬を使用して、しばらく様子を見てもよいでしょう。
成分のアクリノールが患部を殺菌・消毒し、酸化亜鉛が肌を保護するとともに、さらさらとした使用感で肌のすべりをよくします。
| 効能効果 |
|---|
| 火傷,切傷,擦過傷(すり傷),凍傷,乳ぎれ,汗疱(初期のあせも),皮膚のただれ,床ずれ,靴ずれ,あせも,潰瘍,湿疹,肛門周囲炎,会陰裂傷,口唇周囲炎,臍帯脱落後のびらん |
ただし、患者の状態によっても市販薬が使用できるかは変わるため、あらかじめ医師に市販薬で様子を見てもよいか確認するようにしましょう。
ひどい床ずれや床ずれの悪化が起きた場合は、担当の医師かケアマネージャーに連絡しましょう。
特に発熱、患部の周りの赤み、腫れ、痛み、患部の熱っぽさ、ただれ、潰瘍、膿がでるなどがあるときは、すでに細菌感染が起こているおそれもあります。
入院での治療が必要か、自宅で介護しながらの治療が可能かは医師と相談しながら決めることになります。
自宅での治療は相談第一
自宅での床ずれの治療は、介護する側の体力的・経済的な負担や、介護される側の状態・症状などあらゆる面からの検討が必要です。
自宅で治療する場合も、訪問看護や床ずれの防止に役立つ介護用品のレンタル情報など、介護の助けになる情報があるので、一人で抱え込まず医師やケアマネージャーとよく相談することが大切です。
自宅での床ずれの管理は、まず医師や看護師から床ずれの状態や今後のケアについて説明を受ける必要があります。
床ずれの症状によって、治療・管理の仕方が変わるため医師・看護師の説明をよく聞いてください。
その他の床ずれ対策
ドレッシング材や塗り薬だけで治療ができるわけではありません。患者の状態や床ずれの原因に合わせて、さまざまな処置が加わります。
体にかかっている圧を減らす
床ずれの最大の原因は体の一部に体重がかかっていることです。
床ずれになって間もない急性期では、まずは体の圧がかかっている部分の圧迫を減らします。
体圧分散寝具やクッションなどを使ったり、体位変換をおこなったりして、体にかかる圧迫を分散することが大切です。
おわりに
床ずれは出来てしまうと非常に厄介なため、まずは予防が第一です。
在宅介護で床ずれができてしまった場合は、医師や看護師と協力して治療していくことが必要です。
自宅での治療が可能か、入院での治療が必要かは症状や介護する側の負担などあらゆる状況をふまえて判断されます。
床ずれ治療や在宅介護などに不安がある場合は、医師や看護師に伝えるようにしましょう。

昭和大学大学院薬学研究科修了
昭和大学薬学部客員講師
株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局
薬局、ドラッグストアで臨床経験を積み、その後昭和大学薬学部の教員、チェーンドラッグストア協会の教育機関でOTCの研修講師を務める。
【著書】
•現場で差がつく! もう迷わない! ユーキャンの登録販売者お仕事マニュアル 症状と成分でわかるOTC薬
•現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル
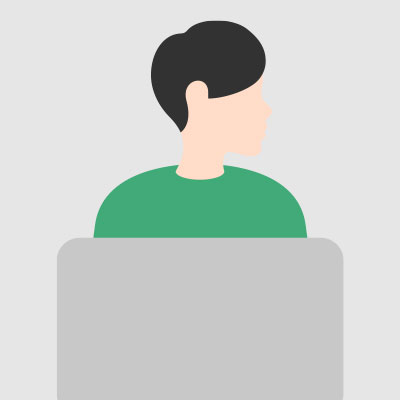
この記事は参考になりましたか?
新着記事
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。


