
脱肛とは?薬で治るもの?脱肛の症状・原因・治療方法について解説
脱肛(肛門脱)とは?どんな症状?
脱肛(肛門脱)とは、痔の一種で、大きくなったいぼ痔が肛門外に出てくる状態のことをいいます。
外に出てきた部分は、皮膚や下着とこすれ合い炎症を起こすと、痛みや出血を伴います。
軽症の間は、排便後、自然に戻るか指で押すと中に引っ込みますが、症状が進行すると、指で押し込んでも戻らず出たままの状態となります。そうなると、肛門内の分泌物がもれ続け、周囲の皮膚がただれてかゆみを引き起こすこともあります。
脱肛(肛門脱)は薬で治る?
脱肛(肛門脱)は、排便時に脱出し、自然に戻る程度であれば、市販の漢方薬を使うこともできます。
ただし、排便後に脱出し毎回指で戻さなければいけなかったり、指で押しても戻らず、肛門外に出たままの状態である場合は、手術が必要となることもあるため、なるべく早く病院を受診してください。
脱肛をほっとくとどうなる?
脱肛の症状がある場合、痛くないうちは放置しがちですが、そのままにしておくと症状が悪化し、脱出した組織が出血や激しい痛みを起こすこともあります。
症状が悪化するにつれ、治療の選択肢が狭まったり、大がかりな処置が必要となることもあるため、なるべく早く対処することが大切です。
脱肛(肛門脱)に効く薬
排便時に脱出し、自然に戻る程度の軽度の脱肛に使える漢方薬を紹介します。
軽度の脱肛に使える漢方薬は乙字湯といい、血液循環を整えて患部のうっ血をとることで、腫れや出血、痛みなどの痔による症状をやわらげ、便の排出をうながします。
乙字湯は、脱肛の症状とともに便秘傾向があり、便が固い方におすすめです。
| 乙字湯の効能・効果 |
|---|
| 体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症: 痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛 |
(※)体力中等度がどのくらいの体力を示すかについては、通常の生活をするのに差し障りがない程度の体力と考えられています。
乙字湯の紹介
乙字湯には、顆粒タイプと錠剤タイプの2種類の剤形があります。
漢方薬特有の味やにおいが苦にならない方は顆粒、苦手という方は錠剤を選ぶとよいでしょう。また、成人(15歳以上)1日あたりの服用量に含まれる乙字湯エキスの量にも違いがあります。剤形や成分量などから、自分に合った製品を選びましょう。
本草乙字湯エキス顆粒-H
| 特徴 |
|---|
| ・成人1日量に含まれる乙字湯エキス|2,200mg ・顆粒タイプ ・1日2回、1回1包 (15歳以上) |
漢方処方「乙字湯」を煎じて簡便に服用できるように、エキス顆粒(分包)とした製品です。6種類の生薬から抽出した乙字湯エキスが、軽度の脱肛、いぼ痔、切れ痔などに効果をあらわします。
1日2回(朝夕)の服用のため、オフィスや外出先で服用することなく続けられます。痔の薬と気づかれにくいパッケージも特徴の一つです。
生後3か月から服用できます。
クラシエ漢方乙字湯エキス顆粒
| 特徴 |
|---|
| ・成人1日量に含まれる乙字湯エキス|2,100mg ・顆粒タイプ ・1日3回、1回1包 (15歳以上) |
成人1日あたりの服用量3包中に含まれる乙字湯エキスの量は、2,100mgです。
漢方薬の味やにおいが苦にならない方や、錠剤タイプは飲み込みにくくて苦手、といった方におすすめの顆粒タイプです。
生後3か月から服用できます。
ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒
| 特徴 |
|---|
| ・成人1日量に含まれる乙字湯エキス|2,000mg ・顆粒タイプ ・1日2回、1回1包 (15歳以上) |
ツムラから販売されている、顆粒タイプの乙字湯です。
顆粒タイプは、1回の服用量が個包装されているため、外出の際の携帯にも便利です。
特徴として、1日2回の服用回数で済むため、お仕事などで昼間の服用が難しい方にもおすすめです。
2歳から服用できます。
クラシエ漢方乙字湯エキス錠
| 特徴 |
|---|
| ・成人1日量に含まれる乙字湯エキス|2,520mg ・錠剤タイプ ・1日3回、1回4錠 (15歳以上) |
成人1日あたりの服用量12錠中に含まれる乙字湯エキスの量は、2,520mgです。
漢方薬独特の味やにおいが苦手な方に向いている錠剤タイプです。
5歳から服用できます。
脱肛(肛門脱)の原因
脱肛(肛門脱)は、肛門の内側にできたいぼ痔(内痔核)が大きくなったものが肛門外に出る状態をいいます。
内痔核は、「便秘やトイレが長くて排便時にいきむことが多い」、「長時間座ったままの姿勢でいる」という場合などにより、肛門部へ過度の刺激や負担がかかると、次第に膨らみが大きくなり、肛門外へ飛び出してきます。
また、内痔核自体も、便秘や座ったままの姿勢が続き、肛門に大きな負担がかかることで発症します。内痔核の原因となるような排便習慣や生活習慣を続けていると、脱肛になりやすくなります。
出産時に脱肛になる場合もある
女性の場合は、出産時のいきみや、生まれるときに赤ちゃんの頭で圧迫されたことなどが原因で脱肛が生じることがあります。
脱肛(肛門脱)と痔の違い|治療方法
脱肛(肛門脱)は、痔の一種で、痔の中で最も多い内痔核の症状のひとつです。
痔は、大きく分けて、いぼ痔、切れ痔、痔ろうの3つに分けられ、いぼ痔はさらに肛門の内側にできるもの(内痔核)と外側にできるもの(外痔核)に分けられます。
| 痔の種類 | 特徴 | |
|---|---|---|
| いぼ痔 | 内痔核 | ・肛門の内側にできるいぼ痔 ・痛みが少ない ・排便時に出血する |
| 外痔核 | ・肛門外にできるいぼ痔 ・痛みがある ・大きく腫れると痛みが激しくなる | |
| 切れ痔 | ・肛門の皮膚が切れたり裂けたりした状態 ・排便時に強い痛みを感じる ・出血は少ない | |
| 痔ろう | ・お尻から膿が出ている ・お尻が熱い ・肛門周辺が腫れてズキズキと痛む | |
内痔核の分類|Ⅰ度・Ⅱ度・Ⅲ度・Ⅳ度
内痔核は、痔核の脱出の程度などによって4分類にわけられています。
| Ⅰ度 | 排便時に痔核が膨らむが、肛門外にはでない |
|---|---|
| Ⅱ度 | 排便時に痔核が肛門外にでるが、排便後は肛門内に戻る |
| Ⅲ度 | 排便時に痔核が肛門外にでて、排便後も痔核を手で押し込まないと肛門内に戻らない |
| Ⅳ度 | 排便の有無に関わらず、常に痔核が肛門外に出ていて、肛門内に押し戻すこともできない |
痔核の治療方法
痔核で病院にかかると、痛みや腫れ、出血をおさえる外用薬(坐薬・軟膏)や、便をやわらかくしたり、炎症をおさえたりする内服薬が処方されます。
薬で治らない場合には、手術が必要となる場合もあります。
手術の方法として、出血を繰り返す内痔核に対しては、注射で内痔核を硬くして、縮小させる「硬化療法」であったり、いぼ痔そのものをゴムで縛って小さくする治療法(ゴム輪結紮法)が行われることもあります。
脱肛などの重度のいぼ痔では、いぼ痔自体を切除する方法(結紮切除術)が選択されることもあります。
脱肛は自分の力で治せる?
いぼ痔が肛門の中にあるうちは、軽度であるため、排便習慣や生活習慣の改善だけで治ることもありますが、いぼ痔が肛門外に出る脱肛を生じた場合は、市販薬での対処もしくは病院の受診が必要です。
また、脱肛は、いぼ痔が外に出たままだと症状が悪化することもあるため、痛くない場合に限り、外に出ている部分を指で肛門の中に押し戻してください。
脱肛の戻し方については、排便後に脱出した場合、肛門をきれいにしてから、便器に座ったまま指でゆっくりと肛門の中に押し戻します。このとき、押さえながら立ち上がるとスムーズに押し戻すことができます。
戻りにくい場合は、トイレの温水洗浄便座機能やお風呂のシャワーを使い、肛門を温めてから押し戻すと戻りやすくなります。ただし、温水は長時間使用しないように気をつけましょう。長時間使用すると、ウイルスや細菌から守ってくれる常在菌も洗い流してしまうため、痔の再発や症状の悪化に繋がります。
それでも戻らない場合は、無理に押し込もうとせず、病院を受診するようにしましょう。
痔を繰り返さないために日常生活で気をつけること
痔の再発を予防したり、悪化させないためには、排便習慣や食生活、生活習慣の改善が大切です。
排便習慣の見直し
◎排便の際に無理にいきまない
便意がないときに排便しようとしていきむと、肛門に余計な圧力がかかり、うっ血して痔の誘引になったり、痔を悪化させたりすることがあります。
排便時には、完全に出し切ろうと必要以上にいきまないようにしましょう。
◎おしりを丁寧に拭く
排便後は、ゴシゴシこするのではなく、紙を押しあてるようにして優しく拭くようにしましょう。
また、便の質などによっては、何回も拭かないと便がとれにくい場合もあるため、必要に応じてトイレの温水洗浄機能を使って温水で洗うようにしましょう。
ただし、おしりの皮膚はデリケートなため、強い水圧で洗ったり、洗いすぎたりしないようにしましょう。
食生活の見直し
◎便秘や下痢にならないよう、食物繊維を多く含んだ野菜や豆類、イモ類、海草類などを多くとりましょう。
◎朝食の後は便意が起こりやすいため、朝食をきちんととりましょう。
◎便秘の解消のためには、十分な水分を摂取することも大切です。
◎下痢を起こしやすく、肛門を刺激しやすいため、香辛料などの刺激物は控えめにしましょう。
◎過剰なアルコールは、症状を悪化させることがあるため、飲酒はほどほどにしましょう。
生活習慣の見直し
◎肛門を清潔に保つために、また、患部の血行を改善するために、できるだけ毎日湯船につかるようにしましょう。
◎長時間座りっぱなしでいると、肛門部がうっ血するため、適宜、ストレッチや散歩などをして、体を動かしましょう。
◎ストレスや疲労をためないように、ストレス発散方法を見つけることも大切です。
◎冬場は、使い捨てカイロを下着の上から肛門の周囲にあてたりして、冷えないようにしましょう。

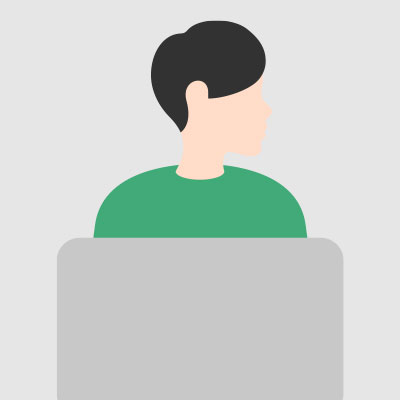
この記事は参考になりましたか?
この記事を見ている方は 他の関連記事も見ています
ご利用に当たっての注意事項
- 掲載している情報は、セルフメディケーション・データベースセンターから提供されたものです。
- 適正に使用したにもかかわらず副作用などの健康被害が発生した場合は(独)医薬品医療機器総合機構(TEL:0120-149-931)にご相談ください。
- より詳細な情報を望まれる場合は、購入された薬局・薬店の薬剤師におたずねください。
- 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラ及び、セルフメディケーション・データベースセンターではその賠償の責任を一切負わないものとします。
掲載情報について
掲載している各種情報は、株式会社ミナカラが調査した情報をもとにしています。出来るだけ正確な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、株式会社ミナカラではその賠償の責任を一切負わないものとします。情報に誤りがある場合には、お手数ですが株式会社ミナカラまでご連絡をいただけますようお願いいたします。 使用されている写真はイメージです。実際の内容と異なる場合があります。





